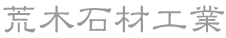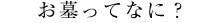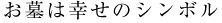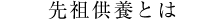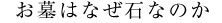ご先祖様は、お位牌とお墓のどちらにいるのでしょう?
人が亡くなったらどうなるか、どこへ行くのか、について、民族学の父・柳田国男先生の著書では、魂は3つの段階をたどる、と書いてあります。その3つのどの段階でも、「大切にお祀り(おまつり)をしてもらうと、わざわいを除き、幸福をもたらす」とあります。また、魂の往く場所、すなわち「あの世」も3つあります。それは、ふるさとの山である「神奈備(かむなび)」、同じくふるさとの海である「妣の国(ははのくに)」、そして、地下にある「黄泉の国(よみのくに)」(根の国)の3つです。
私たちはどの「あの世」に往くのでしょうか?
形の無い魂がふるさとの山や海に帰り、かたちのある亡骸は地下へと、それぞれの「自然」に帰ります。日本人は、この2つの違いを1,500年以上も前からちゃんと知っていて、「浮かぶたましい」と、「草葉の陰(お墓)のたましい」と言う日常語で使い分けてきました。じつはこれは、古代中国の思想です。
「礼記」(らいき)という本があります。この本は、約3,000年前に中国社会の礼に関する諸説を集めた本です。これには、今でも日本で行う一周忌や三周忌も出てきます。その「礼記」には、「魂」(こん)と「魄」(はく)と言う2つの魂(たましい)について書かれています。
「魂」とは「気体のように軽い魂」で天に帰っていくもの、「魄」とは「形のある重い魂」でふるさとの大地に帰るもの、と考えられました。そして、「魄」とは「白骨」を意味します。
また、人の神(たましい)を宇宙の原理の陰陽にあてはめて、「魄は陰の神(たましい)であり、魂は陽の神(たましい)である」と書かれているものもあります。
人が「生きている」ということは、この「魂」と「魄」がひとつになって、精神(魂・陽)と肉体(魄・陰)が活動している状態です。死ぬということは、「魂」と「魄」が2つに分かれてそれぞれ宇宙・大自然のふるさとに帰ることなのです。
私たちはここから縁あって生まれ、そして生きて、やがて死んでまたそこへ帰るのです。
「お盆」といえばご先祖様がわが家に帰ってくる日です。この「お盆」もインド仏教・中国の儒教・道教が混ざり合った行事で、年月を経て、私たちが現在見なれたかたちになりました。
日本では、 「魂」と「魄」に分かれたご先祖様が帰ってくる場所について、「魂」が「お位牌」であり、「魄」が「お墓」であると考えられました。
お墓は、人が亡くなって「魄」というたましいの宿る白骨を大自然のふるさと「大地」へ帰す大切な役割を果たしているのです。

■日本のお墓を愛したモラエス
ポルトガル人モラエスの日本随想記『徳島の盆踊り』(岡村多希子訳・講談社学術文庫)には、現代の日本人が忘れた先祖崇拝とお墓の魅力が、心温まる美しい文章でつづられています。少し紹介します。
—(死者は)「ほとけ」すなわち仏陀となる。一般に口にされる敬称である「ほとけさん」は、自分が生きていた土地や家族を忘れず、好物だった食べ物の味や、好きだった花の香りさえも忘れることなく(家族が)寄せてくれるやさしい想いに感謝し、喜んで彼らを保護する。ここから先祖崇拝が生まれる。
—日本の家族が死者を祀るのは寺院においてではない、墓地の墓のそばや家庭の祭壇においてである。
—(死者の霊は)あらゆるものが見え、聞こえるのであり、もっともふさわしい場所、すなわち自分がかつて住んでいた家や、納骨されている墓で尊崇されることを喜ぶのである。
—日本人が死を前にして穏やかな諦念にひたっていられるのは、死者崇拝のおかげである。・・・死んで家庭の中にその場を占め続け、妻あるいは夫の、子供たちの、孫たちの、曾孫たちの、玄孫たちの、未来の全ての世代の愛情をうけ続けることは、実を言えば、死ぬことではない。生きること、永遠に生きることなのである!
そしてモラエスは、日本のお墓参りの美しい習慣に感動したあと、次のように書いています。
—広大な墓地が無数にあるここ徳島で、墓地巡りが自然と楽しくなって、習慣化した。死者のそばにいると、彼らをとりまく静かな風景の中にいると、・・・私のこころは安らぎををおぼえる、・・・
と。
長くなるので省略しますが、『徳島の盆踊り』には、現代人が失いかけている日本人の「ご先祖様」とともに生きる人々の生活が、いきいきと描かれています。
■日本人と「お墓のこころ」
亡き人に対するお墓やお葬式の儀式、お祀りは、いろいろな民族独自の「死」に対する考え方をもとにしてできています。「人は亡くなるとどうなるか」、「人はどこから来て、どこへ行くのか」、「あの世はあるのか」などという「死生観」、「死後観」、「霊魂観」、「他界観」は宗教や文化の問題になりますが、ここではそれを「お墓のこころ」とよびます。日本ではお墓をつくるのに、大きく分けて三つの考え方がありました。
一、亡き人(死者)の魂を救うため。
二、家族が栄え、幸せになるため。
三、死者のたたりやけがれを避けるため。
大雑把にいうと、一は仏教が日本にもたらしたもの、二は中国の儒教や風水の「先祖祭祀」の影響を強く受けたもの、三は『古事記』や『日本書紀』など古代日本の神話に基づく神道的な考え方、といえます。
ただ「三」については、残念なことがあります。お墓やお葬式を研究する多くの民族学者や戦後の仏教学者たち、それに一部のお坊さんまでが「死者のたたり・けがれ」ばかりを大きく取り上げて「亡き人の冥福や家族の幸せ」のことをすっかり忘れてしまったかのように口を閉ざしている点です。モラエスが感動したように、古来日本人は、お墓や仏壇の前で、亡き人のご冥福を祈り、ご先祖様を供養しながら、ご先祖様とともに生活をする幸せを感じてきました。こうした習慣は、たぶん五・六千年前の縄文時代からあったと考えられます。だから、日本人が「たたりやけがれ」のためだけにお墓をつくった、とはどうしても思えないのです。モラエスもきっと、そう感じたはずです。
■墓地で発見したこと
全国各地に出張した時、よくそこの墓地をたずねますが、今ではそれが、とても「楽しい時間」になっています。墓地やお墓を「こわい」と思ったことはないのですが、初めのうちは少し薄気味悪くて、決して居心地がよい場所とも思えませんでした。それが突然、あることに気付いて、すっかりお墓が好きになりました。
蓮華台のあるお墓の前に来た時何気なく、「なぜ蓮華台をつけるのだろう?」と考えて、ハッと気付いたのです。「このお墓に眠っている人は、立派にホトケ様となって、今は極楽往生で安らかに暮らしているんじゃないか!」と。
蓮の華は、極楽浄土へ往生する時、亡き人がこの世から乗っていく「専用の乗物」です。また、仏教そのもののシンボルであり、ホトケ様のシンボルとして仏教には必ず「蓮華台」が付いています。
そうすると、この蓮華台の付いているお墓に眠っている人は、立派に「ホトケ様となった」(成仏した)ことになります。思わず小さな声で「よかったですね」と声をかけました。そして同時に、このお墓を建てた家族の人の気持ちがよくわかりました。
「残された家族はみんな、亡き人の幸せをひたすら願ってお墓を建てているのだ」と。
すると、とたんに、お墓や墓地が今まで違って、「すばらしい場所」に見えたのです。とりわけ「お墓」には、亡き人の、あの世での幸せを願う家族一人一人の気持ちがギュッと凝縮されているではありませんか。
お墓はまぎれもなく「幸せのシンボル」なのだ、と感じられました。このことがあってから、お墓や墓地が大変好きになりました。ポルトガル人のモラエスはきっと、キリスト教世界に無い、日本の「美しい心」に魅了されたのでしょう。そして彼は日本で生涯を終え、こよなく愛した徳島のお墓の土に今も安らかに眠っています。
■三内丸山遺跡のお墓
縄文時代の定説を覆した「三内丸山遺跡」(さんないまるやまいせき・青森県)で変わった墓地を見て、本当に感動しました。
集落の中央を通る広い道の両側の斜面に、向き合うように並んだお墓の列が、最初50メートルほど見つかりました。ところが、その後この道は400メートルほど発掘され、その先は未調査です。しかも道の幅が、大型車など無論無かった5,000年前に、なんと15メートルもありました。今の国道並みの広さです。
これをどのように考えたらよいのでしょう。考古学の見方は知りませんが、この情景を見た時、すぐ「あっ、これは村全員が定期的にお墓参りをしたに違いない」と感じました。そうでないと、こんな広い道は必要ありません。それで「村中の人がお墓の参道を、行列しながらお参りするためなんだろう」と思いました。
しかしこの道は海岸へ続き、海の幸やさまざまな珍しいものが入ってくる大切な道なので、大勢の人が行き来し、大がかりな作業もしたのなら、「お墓参り」だけが目的ではなかったかもしれません。それにしてもなぜ、生活に必要な物資を運ぶ道路の両側に、整然と列をなして、亡くなった人を埋葬したのでしょうか。縄文人はきっと、亡くなった人達に、もっとも大切な自然の恵みを見せ、生きている人々とともに生活していたのではないでしょうか。
これが日本人の「死生観」の原点と思います。だから、民俗学者や仏教学者がいうように、死者の「けがれ」や「たたり」を恐れてお墓をつくったり、遺体を野山に棄てるのが日本人のお墓の原点だとは、どうしても考えられないのです。
弥生時代の「吉野ヶ里遺跡」(佐賀県)で、首長の小高い墳丘墓と、多くの甕棺が埋葬された墓域を見た時にも、三内丸山のお墓と同じことを感じました。
確かに長い歴史の中では天災・飢饉・戦乱時に、野山に死者を棄てたかもしれません。しかし、日本人は、本来、亡き人とともに暮らしました。例えば、自分の土地にお墓をつくる「屋敷墓」の風習が全国にたくさんあったのを見てもわかります。(今は法律で規制されています。)
■お墓が「幸せのシンボル」に見える人
かつて、日本人は、「死んだらご先祖様になって、子や孫の面倒を見る」といいました。そんな老人がいたのも、ご先祖様とともに「幸せに生きる習慣」が日本にあったからです。
今は、ほんの少し、そのことを忘れているのでしょうか。こんなすばらしい習慣を、お墓参りのとき、家族そろって思い出して欲しいのです。お墓が「幸せのシンボル」に見えると、それは自然に身に付きます。

■供養ってどんなこと?
私たちは「供養」(くよう)という言葉をたいてい「先祖供養」の意味で使っています。同じような供養に「追善供養」(ついぜんくよう)や「卒塔婆供養」 (そとうばくよう)があります。しかし、「どういうこと?」と聞かれたら、ちょっと困ります。まず、辞書を見ましょう。
『広辞苑』(岩波書店) には、「三宝(仏・法・僧)または死者の霊に諸物を供え回向(えこう)すること」、「敬・行・利の供養、仏・法・僧供養などの種類がある」とあります。でも、これ ではなかなか読めませんし意味がわかりません。「死者の霊に諸物を供え回向すること」はどうにか分かりそうですが、回向ってなんでしょう?そこで『岩波国 語辞典』(岩波書店)を引くと、「死者の霊に供え物をして、死者の冥福(めいふく)を祈ること」とあり、冥福によみ仮名がついています。これなら「先祖供養」に近いのですが、冥福は「・・・?」です。では、日本の「先祖供養」はどのようにできたのか、それからみてみましょう。
■インド仏教の卒塔婆供養
二千四百年ほど前、お釈迦様が八十歳でご臨終の時、弟子たちに最後の説法をされ、「私の遺骨の供養(崇拝)には、お前たちはかかわるな」と言われました。 それから、葬儀の方法を説かれ「火葬のあとストゥーパをつくり花輪・香料をささげて礼拝するなら、長いご利益(りやく)と幸せがある」といわれました。そこで信者の王たちによって仏舎利(ぶっしゃり・お骨)は八つに分けられ、その後二百年の間に八万四千の塔廟(とうびょう)、つまりストゥーパ(卒塔婆)が 建てられました。残された在家の信者たちは石柱や欄干の石を寄進し、いつしかお坊さんも熱心に卒塔婆を供養し礼拝しはじめたのです。これが「卒塔婆供養」 (お墓の供養)のはじまりです。
そこでインド仏教の死者供養ですが、まずお釈迦様のお骨(仏舎利)を納めるストゥーパ(卒塔婆)に花やお香を供えて供養・礼拝して、自分の功徳(善い行いによる徳)を積みます。その功徳によって亡き父母たちのあの世での幸福(=冥福)を祈ったのです。
この仏舎利やストゥーパ(塔)を供養すると大きな功徳があると説いたのが、有名な『法華経』(ほっけきょう)という大乗仏教のお経です。
■中国仏教と先祖祭祀
中国に仏教が伝わり、サンスクリット(古代インド語)の「プージャ」という言葉が「供養」と訳されましたが、じつは中国では、仏教が入る前から「供養」という言葉が儒教の書物の中にあったのです。
お釈迦様が生まれる前の、紀元前二千五百年ころにできた『礼記』(らいき)には、朝廷がお年寄りや障害ある人たちを扶養することを「供養(きょうよう)」といっています。また、紀元八十年ころできた『漢書』では、先祖の霊廟に供物を供えることを「供養」といっています。
中国では三千年前の「殷」(いん)の時代には「先祖祭祀」という大切な儀式がすでにありました。先祖を祀ることは、現代中国になるまで、国と家庭のとても大切な行事でした。それが仏教の教えと結びついたのです。
『広辞苑』にあるように、インド仏教では、仏・法・僧の「三宝」を供養することが本来の供養でした。だから、「仏」であるお釈迦様の遺骨(仏舎利)とその お墓(ストゥーパ=卒塔婆)の供養があくまで中心なのです。人々はその供養をして功徳を積み、それを亡き父母へ差し向ける(回向する)ことで「死者供養」 をしたのです。
ところが中国仏教となると、直接、先祖や亡き父母を(霊廟で)まつる儒教の「先祖祭祀」の考え方が仏教に取り入れられ、この大きな変化が日本に影響を与えます。
このようにインド仏教の言葉を漢文に訳すとき、中国にあったもとの意味をそのまま仏教に採り入れることがしばしばありました。「供養」はそのよい例です。
■日本独自の先祖供養
日本へは千五百年前に中国仏教が伝わり、明治になるまで漢文のお経だけが使われました。それでインド仏教と儒教それに日本独自の習慣とがバランス良くミックスされた先祖供養となりました。これは他の仏教国では見られないものです。
日本では、お仏壇にご本尊さま(仏)をまつり、ご先祖様のお位牌や浄土真宗のように法名軸(ほうみょうじく)をまつります。これは儒教の「霊廟」(れいびょう)とインド仏教のお釈迦様(仏)への供養がミックスされています。またお墓参りをしてご先祖様を供養する習慣も、インドのストゥーパ(卒塔婆=仏舎利を納めたお墓)供養と、中国の先祖供養(祭祀)が結びついたかたちです。
しかし、中国では、お墓参りは仏教とは関係がありませんし、よほどではないかぎり霊廟(日本の仏壇にあたる)にご本尊さまをお祀りしません。たしかにインドや中国の供養の考えが入っていますが、インドや中国のやり方どおりでないのが、日本の先祖供養の特徴です。
■地獄と追善供養
お釈迦様のころにはなかった教えが、その後出てきました。「六道輪廻」(ろくどうりんね)や「地獄と極楽」などです。
人が亡くなると、次に生まれ変わるまでに四十九日間は、七日ごとにあの世(瞑府)の七人の王による裁判を受けて、次に生まれる世界が決まる、というので す。そのために生前の善行と悪行を判定します。もちろん最善の人は裁判なしに極楽へ直行できますが、極悪非道の人もまた裁判抜きでそのまま地獄に堕ちます。ところが中善・中悪の人の行先は、天界・人間界・阿修羅界(あしゅらかい)・餓鬼道(がきどう)・畜生界(ちくしょうかい)・地獄の六つの世界(六道)があります。
この六つの世界を繰り返し無限に生まれ変わることを「六道輪廻」(ろうどうりんね)といいます。しかし、極楽へ往くともう輪廻はありません。これが「解脱」(げだつ)で、輪廻からの解放です。
冥界の王たちは、さまざまな方法で生前の行いを突きつけて死者を厳しく責めますが、最後に必ず、遺族による「追善供養」(ついぜんくよう)のことを調べます。追善供養によって、あの世(瞑界)や六道のどこかに生まれ変わって苦しむ故人を救うことが出来るからです。人が亡くなって、四十九日、百ヶ日、一周忌、三回忌、十三回忌・・・・お盆、お彼岸に行う供養が「追善供養」です。
ちなみに、百ヶ日、一周忌、三回忌はみな儒教の習慣で、先ほどの『礼記』(らいき)に出ています。ただ、百ヶ日は中国になく死後百日目くらいが「卒哭」(そっこく)の日に当たり、日本でこれを「百ヶ日」といったようです。
『地蔵本願経』(じぞうほんがんきょう)というお経に、「追善供養をすると、その七分の一だけ亡き人に回され、残りの七分の六は供養をした本人の功徳になる」とあります。ということは、四十九日間の間、七日ごと七回の追善供養をすると、ちょうど満願になり、晴れてめでたく極楽往生できる仕組みになっています。
このお経にはまた、「生前に、あらかじめ自分の死後の供養をしておくと、全て功徳になる」とあります。これは「逆修」(ぎゃくしゅう)「預修」(よしゅう)といいます。生前に戒名を頂いて、お位牌をつくり、お墓を建てておこなう法要のことです。
■お墓供養の意味と仕方
では、お墓の「供養」はどうやるのでしょうか。密教では、お水・塗香(ずこう)・お花・焼香・飲食(おんじき)・灯明(とうみょう)の六供養をあげます。これが基本です。しかし、各宗派とも少しずつ違います。詳しくは各宗派の手引書を見て下さい。
たとえば日蓮宗では「死者の冥福を祈り成仏を期す信仰のいとなみ」、「善根功徳をつみ供養物などをささげる」仏事とあります。お墓掃除の後、お水、お花、 お線香、お供物(菓子と果物)を供え、数珠をかけて合掌し「お題目」を唱える、と『仏事供養のこころえ』にあります。そして、「卒塔婆供養」をすすめます。
浄土真宗では、亡き人は阿弥陀様のよってすでに浄土に往っているので追善という考えがありません。霊も認めないので、墓誌は「法名碑」(ほうみょうひ)、 墓石は「南無阿弥陀仏」と刻むことをすすめ、「卒塔婆供養」をすすめません。お墓掃除や供物は日蓮宗と同じですが、合掌して「お念仏」を唱えます。そし て、お墓は「かけがえのない命を伝えて下さったご先祖に感謝しつつ、その命を精一杯輝かせて生きてくれ、というご先祖の願いを聞く場所でもあります」、と 『仏事のイロハ』(本願寺)に書かれています。
お墓の先祖供養は、ご先祖様の冥福を祈り、尊い生命を残してくれたご先祖様を自分の身体をとおして感じ、ご先祖様を大切にすることだと、思います。お墓参りとその心を代々、子供たちへ伝えているかぎり、すばらしい幸福な家庭になると信じています。亡き祖父母や父母と、家族のみんなが信じ合えてこそ、人として生きている意味の第一歩みがあるからです。
それが本当の「家族のきずな」だと思います。

何年か前ステンレスやセラミック(陶磁器)製のお墓が新聞やテレビで話題になりした。しかし、サッパリ人気 がなくてすぐに消えました。日本人はどうしても、「お墓は石で」という気持ちが強く石以外は受け付けません。それは、なぜでしょうか?
日本は木の文化、ヨーロッパは石の文化といいますが、日本の「石文化」に注意して見ると、日本にも驚くほどたくさんの石の文化が全国各地に残っています。もちろん、巨大な石造モニュメントや、ピラミッド、石の宮殿、石の建物で都市を作った歴史は日本にはありませ ん。しかし、日本には古代から、石を「聖なるもの」として斎(いつ)き祀(まつ)った遺跡がいたるところにあります。
たとえば、神霊の依り代(よりしろ)という「磐座」(いわくら)「石境」(いわさか)「磯城」(しき)、縄文時代の「環状列石」(かんじょうれっせき・古代人の墓)、蘇我馬子の墓という「石舞台」(奈良・飛鳥)の巨大な石の古墳、あるいは中世から流行する道祖神や石仏などを含めると、数え切れないほどの石造物や自然石があります。
『古事記』には「石」「岩」「磐」という字がとてもたくさんあり、これは「木」と比較にならないほど多いのです。
『古事記』にある日本最初の「墓石」のお話の前に、日本列島と神々の誕生を「神代」(かみよ)の物語でみましょう。日本列島は天の神々が、イザナギの命 (みこと)という男の神様とイザナミの命という女の神様の二神に「国づくり」を命じて生まれました。イザナギとイザナミが天上から下をのぞくと、そこには何もなくドロドロした油の様な世界でした。そこで天の浮橋(あめのうきはし)から天の沼矛(ぬばこ)を差し込み、かきまぜて引き上げると、矛の先からコロコロと塩が固まるようにできたのがオノゴロ島です。二神はその島に降りて、天の御柱(あまのみはしら)を立て、「柱の左右から回って出会ったところで国を生もう」と誓います。
まず、淡路島、次に顔が四つある伊予の島(愛比売・えひめ、讃岐・さぬき、粟・あわ土佐=四国)、・・・筑紫の島も顔が四つ(筑紫・つくし、豊・とよ、 肥・ひ、熊曽・くまそ=九州)・・・最後に秋津島(あきつしま=本州)で、日本には八つの島々からなる「大八島国」(おおやしま)が誕生しました。国生みが 終わるといろいろな神々を生みました。石土・風・海・木・野・鳥・穀物などの神々で、イザナミは「火(迦具土・かぐつち)の神」を産んだ時、御陰(ほと)を焼かれて病気になりました。その間も水や食物の神々を生んで、全部で四十もの神々が生まれました。
ここからが日本最初の「墓石」の神話です。
イザナギはイザナミの亡骸の枕辺(まくらべ)で「美しい妻が火の神と引き換えとは!」と泣き、涙から生まれたのが泣沢女(なきさわめ)の神で、葬式の「泣き女」のはじまりです。イザナミは亡くなると、出雲の伯伎(ははき)との境にある比婆(ひば)の山に葬られました。
イザナギは妻に会いたくてあの世の「黄泉国」(よもつくに)に行くと、イザナミが出てきました。イザナギは「愛しい妻よ、私たちの国づくりはまだ完成していない。どうか帰ってきてくれ」と頼みます。イザナミは「なぜもっと早く来てくれなかったの。もう手遅れです。私はあの世の食べ物を食べてしまったので、もどれません。でも、わざわざおいでになったのですから、黄泉の国の神様に相談します。決して私を見ないで!」といって宮殿の中に入りました。長く待たされたイザナギは、櫛の一本を折って 灯をともすと、そこにはウジ虫がわき、身体には八つの雷(いかづち)が宿るイザナミの亡骸があったので、驚いてイザナギは逃げました。イザナミは「私に恥をかかせた」と、黄泉の国の魔女たちに追わせ、イザナギがなんとか逃れると、次には黄泉の国の軍隊を差し向けました。それもなんとか逃げてきたとき、 イザナミ自身が追ってきたので、イザナギは千人でやっと動かせる巨大な「千引岩」(ちびきいわ)で出口を塞ぎました。この千引岩が、神話に出る「墓石」の 始まりです。
そこでイザナギとイザナミは、千引岩(墓石)を中にはさんで最後の別れの言葉を交わしました。
イザナミ「あなたがこんな仕打ちをするなら、あなたの国の人間を日に千人殺します!」
イザナギ「あなたがそうするなら、私は日に千五百もの産屋(うぶや)を立てて見せる!」
これは一日に千人が死に、千五百人が生まれることですが、「人は死ぬ運命にあるが、日本の国は人の数が増え続けて栄える」という神話的予言です。このあとイザナギが死の穢れ(けがれ)を身禊(みそぎ)すると、天照大神(あまてらすおおみかみ)、月読の命(つくよみのみこと)、スサノヲの命などの神々が生まれ、天の岩戸や八俣の大蛇(やまたのおろち)退治などのおなじみの神話が展開します。
さて、神話の「千引岩」つまり「墓石」に込められた意味とはどんなことだったのでしょうか。それは私たちが今使っている墓石の源流となっている点に注意してください。
第一に千引岩(墓石)は、イザナミの命が往った「黄泉の国」の出口を塞ぎ、死者がこの世に自由に出てこれない役割をしています。また、墓石をむやみに開けてのぞいてはいけない、死者が大地のふるさとで安からに眠っている邪魔をしてはいけない、という意味もあります。
二つ目は、千引岩はあの世とこの世を分けるちょうど境界の役目があります。墓石の前にぬかづくのは、死者の世界と向き合うことですから、普段と全く違う状況で、亡くなったかけがいのない家族やご先祖様とともに過ごす、人間として大切な時間という意味があります。境界石はのちに「道祖神」「賽の神」(さえのかみ)や墓地の入り口の「六地蔵」、四つ辻・村のはずれのお地蔵様などになります。どれも知らない異界と日常の世界とを隔てる石という意味です。
外敵や疫 病・疫病神の侵入を防ぎ、あの世で苦しむ死者を救い、知らない世界へと旅立つひとや、そこに暮らす人々の生活を守るなど、さまざまな民俗、仏教、神道の意味が込められています。
ちなみに、「賽の河原」(さいのかわら)は仏教的なこの世とあの世の境界で、お地蔵様は幼くして亡くなった子供たちの苦しみを救うためにそこにいますが、 千引岩で出口を「塞い」だ「塞」(さい)と、賽の河原の「賽」(さい)は字がとてもよく似ています。庶民の感覚では、そんなことから塞の神(さえのかみ・ 道祖神)と村のはずれのお地蔵様とが習合して、いつの間にか同じ意味に受けられるようになったのかも知れません。
第三は、千引岩も墓石も、生きているものと亡くなったものとが会話するちょうど仲立ちの役割をする石で、これがもっとも大切な意味です。『古事記』では、イザナギとイザナミの会話は日本の将来の予言ですが、お墓は本来「魂の会話」をするところだと思います。それは難しいことではなく、人と人が本当に信頼し、お互いにかけがえのない大切な存在であることを確認しあう会話のことです。
亡くなった肉親の魂と、残された家族とが、心の中で素直に会話するところがお墓です。それが「家族のきずな」の始まりだと信じています。神話は、お墓(千引岩)をはさんで死者と生者が会話することの大切さを教えてくれているのです。
日本人は神代のむかしから「石」に霊が宿ると考えてきました。だから、神霊が宿る「磐座」(いわくら)を石でつくり「千引岩」が最初のお墓となったのです。日本には八百万の神々がいますから、自然界のあらゆるものに霊が宿っていますが、石は特別な霊力があると思われたのです。
日本人が古代からお墓を死者の霊魂がやどる依り代の「石」で作るのは、「石」の霊力を信じる伝統があったのです。それは一朝一夕に失われるものではありません。それが2千年の伝統の重みです。
「お墓は石」という日本人の心情はこうした神話と歴史の背景があったのです。
※著作権は「石文化研究所 小畠宏允先生」に帰属します。無断で複製・転載はご遠慮下さい。